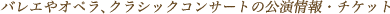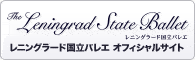~華麗なるロシア音楽~ ウクライナ国立歌劇場管弦楽団
あの大熱演を再び。
ウクライナの至宝、ウクライナ国立歌劇場管弦楽団が大迫力で贈る、スラヴの魂!
〝スラヴの母〟ウクライナ
まるで、うねりを打って押し寄せる大波のような音の厚み。ときに、優しさと懐かしさをたたえながら胸にしみ込んでくる民謡風の響き。そして、歴史と風土の中で育まれた精神をどこまでも守り続けようとする一徹な、内なる熱い魂。チャイコフスキーをはじめとするスラヴ人の音楽には、いつ聴いても心揺り動かされる〝エモーショナルエッセンス〟が溢れている。
ソ連崩壊にともなってウクライナが独立して早19年。もともと民族意識が強く誇り高い土地柄であると同時に、人々は文化的意識も高い。
私たちがウクライナの首都キエフを訪れていくつかの文化施設に足を運んだとしよう。名だたるところには「タラス・シェフチェンコ記念」という冠名が付いていることに気づくだろう。ウクライナ人が敬愛してやまない国民詩人の名だ。キエフの高台にあるウクライナ国立歌劇場も「タラス・シェフチェンコ記念」の名を冠し、正面入口には彼の胸像が飾られている。つまり〝この歌劇場こそがウクライナの誇り〟であることを示しているのだ。
ソ連邦時代を知っている人たちにとっては、現代のロシアもウクライナもイメージの中では一緒になってしまいがちだが、ウクライナには〝スラヴの母〟という思いがある。本当のスラヴの精神や生活はここから四方八方に広がった、という意識だ。旧ソ連時代、名だたる音楽家たち(リヒテルやオイストラフなど)の多くがウクライナ出身であったこともよく知られている通りだ。
チャイコフスキーとウクライナ
その〝スラヴの母〟意識に支えられて、ウクライナ国立歌劇場管弦楽団が今回の公演に持ち込んだプログラムは、チャイコフスキーとラフマニノフ。
実はチャイコフスキーの家系はウクライナに発している。祖父の代に伝統的なウクライナの苗字であるチャイカ(カモメの意)という名をロシア風に改めたのだという。自作のオペラをキエフのウクライナ国立歌劇場で上演することにしたのも、このことと無縁ではないし、実際にその演奏に触れたチャイコフスキーが「モスクワの演奏に引けを取らない」と舌を巻いたというから、チャイコフスキーも自らの出自を誇りに思ったに違いない。
チャイコフスキーの曲目は序曲「1812年」と交響曲第4番。「1812年」はナポレオン率いるフランス軍とそれを迎え撃つロシア軍の激しい戦いを描いた作品で、「ラ・マルセイエーズ」とロシア帝国国家が入り乱れて現れ、眼前に戦いが広がる。また、第4交響曲はチャイコフスキーの「運命交響曲」。自らベートーヴェンの「第5」にヒントを得たと言っているように、チャイコフスキーなりの運命との葛藤とその勝利が描かれている。
ミシュクがラフマニノフで競演
今公演の目玉のひとつが、ピアノのウラジーミル・ミシュクの登場だ。久々に日本のファンの前に姿を現わす。しかも、演奏曲はラフマニノフの第2ピアノ協奏曲だ。ラフマニノフはチャイコフスキーを敬愛し、その影響を受けつつ独自の作風を築き上げたが、この協奏曲はまさにラフマニノフの濃厚なロマン性と華麗な世界が示された傑作。ロシア・ロマン派音楽の代表だ。大型ピアニスト、ミシュクがその真の姿を見せてくれるに違いない。
ウクライナ国立歌劇場管弦楽団+首席指揮者ヴォロディミル・コジュハル+ウラジミル・ミシュク。心拍数が上昇すること間違いなしの、熱い演奏の数々になる。